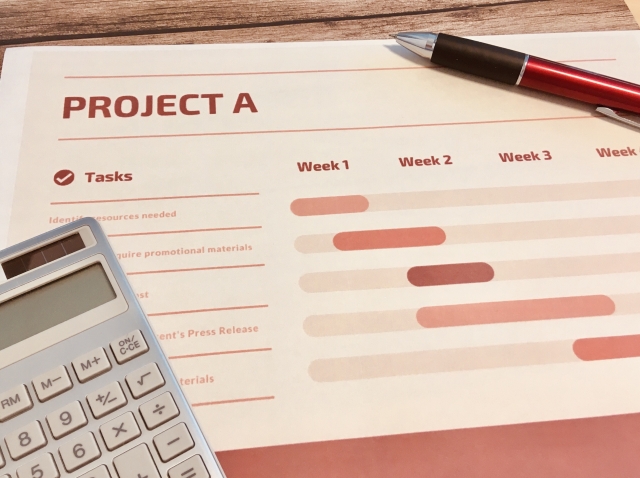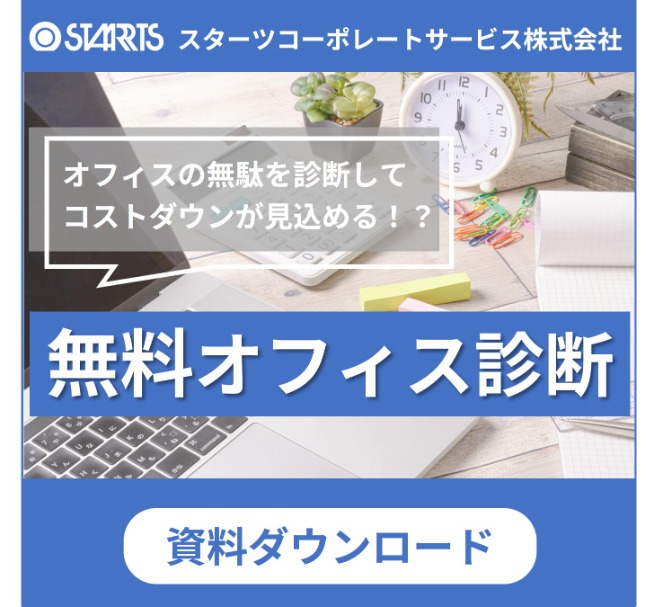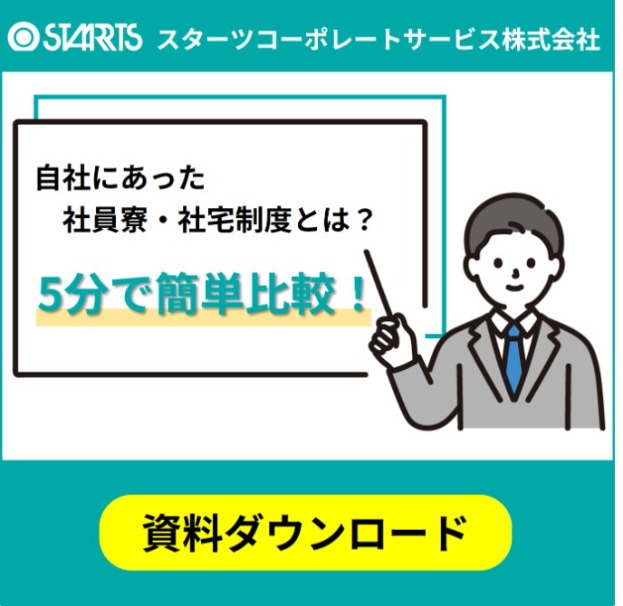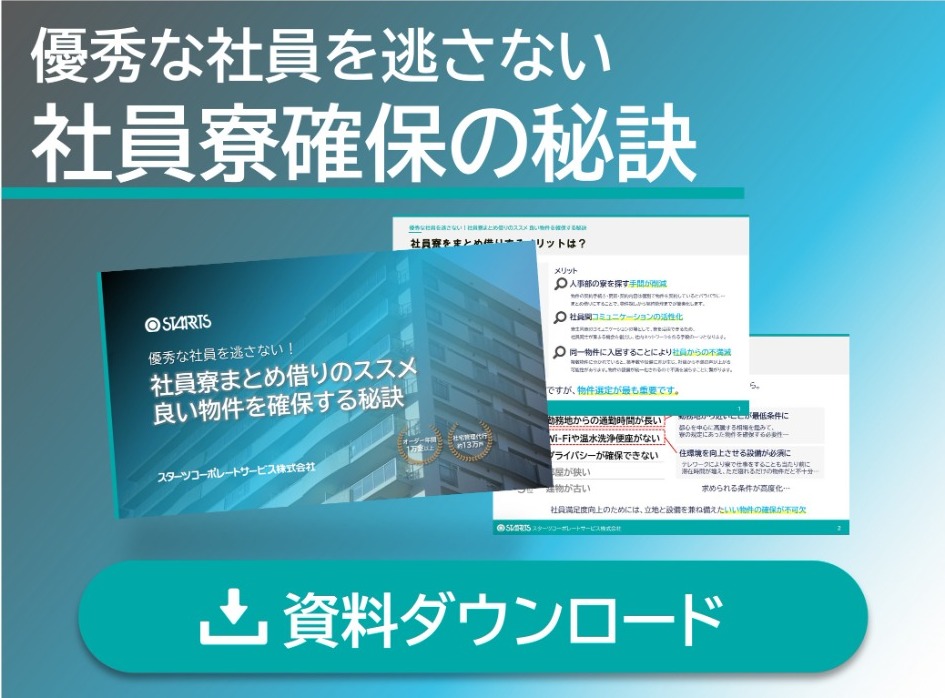「転職サイトを見る前に、自分の会社を見てみよう」人事・総務の責任者座談会~社員のためにしていること、はなしました~

会社の人事・総務部は、社員の笑顔を支える縁の下の力持ち。
そんな彼らが、なにを考え、社員を思い、働いているのか。
今回は3社の責任者クラスのみなさんにお聞きしました。

人財部長 森田 謙二さん
インドネシア、カタールなど海外での約10年の駐在経験の後、今年帰国し現職に。日揮グループ全体の人事に携わる。
日揮コーポレートソリューションズ株式会社は、エネルギーや産業インフラ関連のプラント・施設の設計、資機材調達、建設などを担うエンジニアリング企業「日揮グループ」の中で、コーポレート機能業務を担当する会社。
以下、緑で記載

総務部 長崎 尚子さん
宅配センター、広報・CSR、内部監査などを経て現職。施設管理から、福利厚生、文書管理まで働く環境作りを担当。
日本生活協同組合連合会は、日本各地の生活協同組合(生協)が加入する全国連合会。生協とは、より良い暮らしを実現するために消費者が組合員として出資金を出し合い、協同で運営・利用する組織。
以下、ピンクで記載
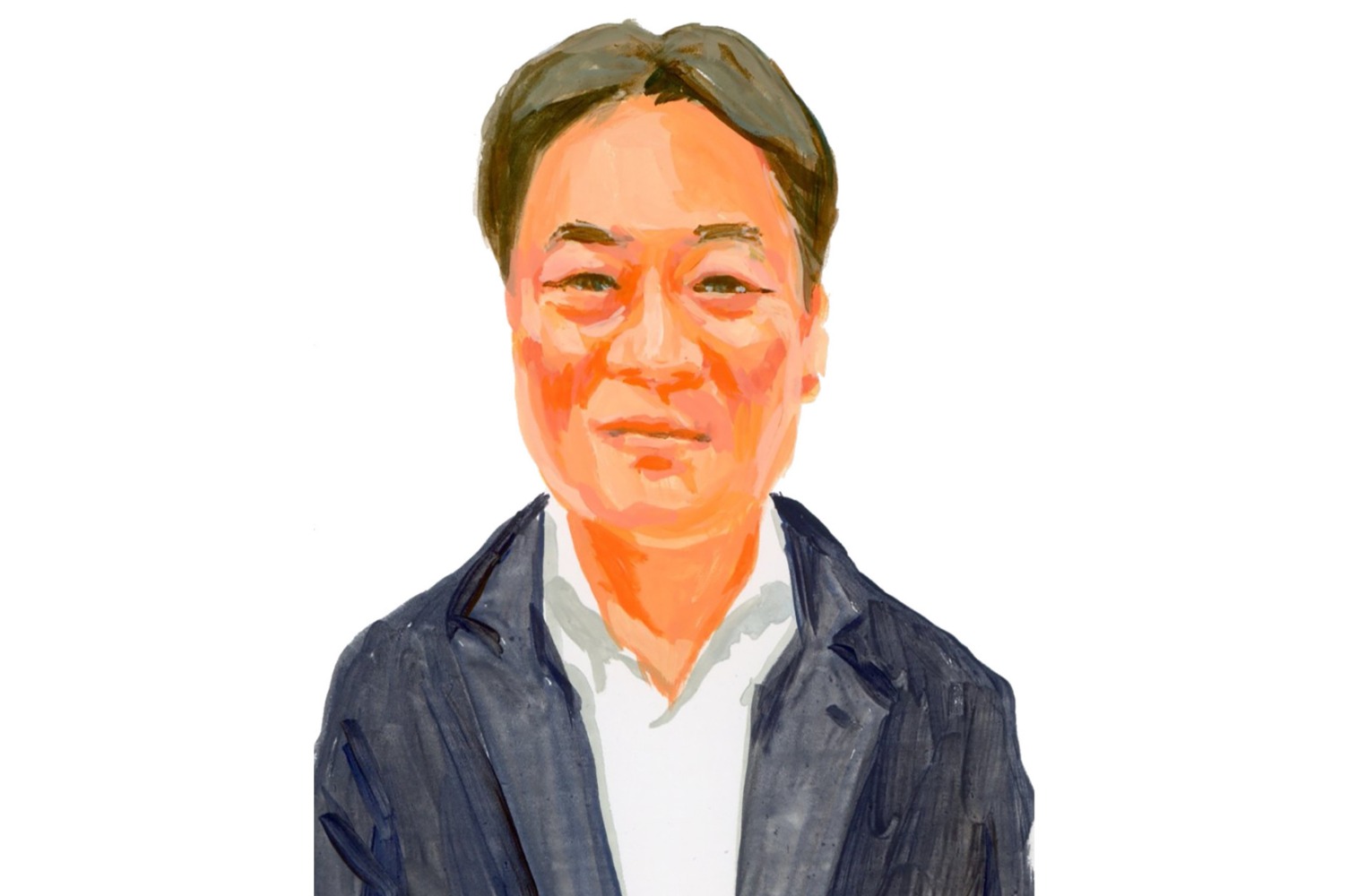
人事部 次長 山田 英一郎さん
営業、総務、関係各社の管理職などを経て人事部に。現在は社員の異動、評価や人事制度改革などに携わっている。
出光興産株式会社は、ガソリンをはじめとする燃料油や、電力、風力や太陽光などの再生可能エネルギー、資源などの分野において、多様なエネルギーと素材の開発、製造、販売を手がけている。
以下、青で記載
Contents

社員の働きやすさを支援!
スターツが企業不動産の課題を解決
無料相談はこちらから
コロナ禍で広がった「働き方」の選択肢
今日はよろしくお願いします。
はじめに伺いたいのは、コロナ禍での変化です。みなさんの会社ではどんなところが変わりましたか?
山田: いちばんに言えるのは社員の働き方ですね。
リモートワークが普及して、オフィスに出社する社員は全体の半数ほどになりました。

森田:
私はちょうどコロナ前に海外へ赴任して、今年本社へ戻ってきたのですが、
皆がネクタイをせずに働いているのに驚きましたね。
コロナを機に、働くうえで「こうあらなければ」という画一的なルールがなくなって、
個人で選べる働き方の範囲が広がったのかなと。ネクタイもその象徴のように感じています。
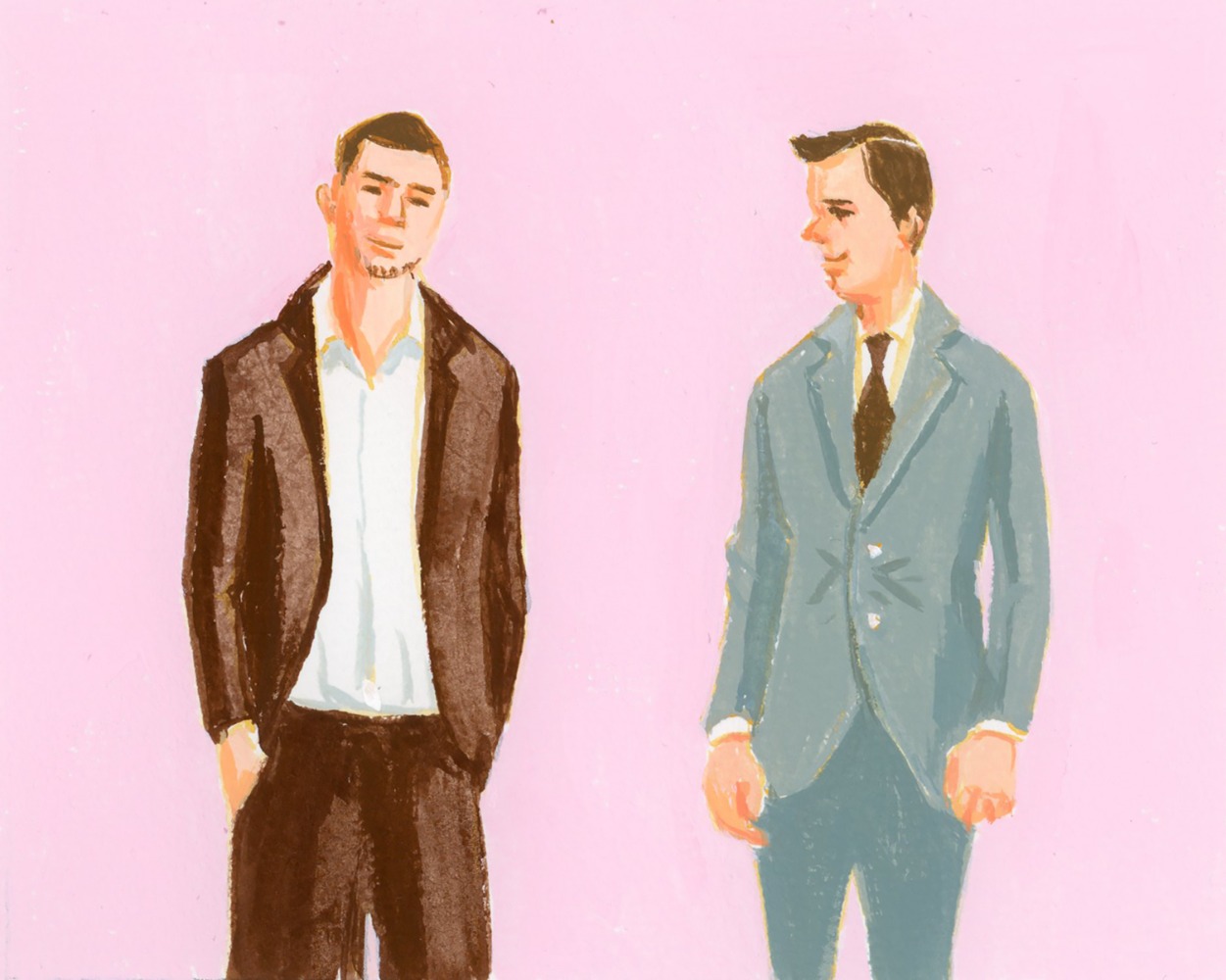
長崎:弊会も以前は身だしなみの基準がありましたが、
それを刷新し、「組織の顔としての自覚を持って、TPOに合わせた服装を適切に選択できる」ことにしました。
働き方が変わる中で、細かな規程はあえて設けず、職員一人ひとりがそれぞれの持ち味を生かして
自律的に考えることを大切にしています。
また、テレワークが普及する中で、チャットなどの非対面のコミュニケーション方法が浸透しました。
ここには、まだ戸惑いを感じている職員もいます。
森田:やはりミスコミュニケーションの不安はありますね。
私も今年、数年ぶりに本社へ戻った際、リモートワークで新しい社員と顔を合わせる機会が少ないので、
なかなか顔と名前が一致せず苦労しました。
山田: 昔は出社して顔をつき合わせることで、仕事も人脈も自分で広げていくことが当たり前でしたが、
今はそれも個人の判断に委ねられるようになりましたね。
生産性の観点で直接のコミュニケーションはやはり重要だと考えていますが、
それをどの程度、社員に促していくべきかは考えたいところです。
それと、よい変化としては、ペーパーレス化が進んだこと。
フリーアドレスにより荷物の軽量化が進み、書類を保管できる場所がなくなったのがきっかけです。
私自身、昔は紙が大好きな人間でしたが、今ではすべてデータ化し、P Cとタブレットで仕事をするように。
役員も含め多くの社員がiPadを持って会議に参加しています。
昇進だけが「やりがい」じゃない。働く価値観も変化して
長崎:働き方の話と同様に、職員の「働きがい」のとらえ方も変わってきていますよね。
私自身もそうですが、昔ってとにかく昇進することがやりがいで、
業績が上がったり、自分の決定権が増えたりすることに楽しみを見いだす人が多かったと思います。
でも、今はそうではない。
仕事だけではなく「人生」という括りの中で、その人がなにを大事にしているのかによって、
働くことに対する価値観はさまざまです。
職員一人ひとりと対話を重ねることでそれを理解し、フィットする働き方を見つけていかなければならないですし、
そのためにより丁寧なコミュニケーションが必要になってきたと感じています。
山田: おっしゃる通り、私たちの世代はライフキャリア=ワークキャリアそのものでしたが、
今は個々のライフキャリアの一部にワークキャリアがあるという認識に変化していますよね。
なかでもこの頃感じるのは、転居を伴う異動に抵抗のある社員が増えたこと。
弊社は全国、全世界に拠点があり、そこでは必ず人が働いているわけですが、最近は特にそこの人材配置が難しい現状があります。
昔は行けと言われた所へ、ふたつ返事で飛んでいったものですが、
結婚して、共働きで暮らしている今の世代は、子育てのワンオペ問題や保育園問題、そして親の介護問題など、
暮らしの事情が込み入って、今いる場所からなかなか動きづらくなってきている。
現代ならではだと思います。

森田:弊社も、ツンドラからジャングルまで世界中に建設現場がある中で、
やはり現場駐在の人材確保が事業運営上の大きなネックになっています。
今は駐在員に休みを多く付与したり、処遇を上げたりすることで、人員をなんとか確保しようと取り組んでいるところです。
山田: 海外や地方で働く経験って、本人の成長にとってはすごくよいことだと思うんです。
私は、仕事における能力の向上には、身につけた知識やスキルに対して「経験」の掛け算をすることが不可欠だと考えています。
まったく知らない土地で新しい人に出会い、新しい仕事に挑戦することで、人は飛躍できる。
そのことを理解してもらうために、弊社では対話を重要視しています。
個々が抱える暮らしの事情をできるだけ考慮しながら、その人のキャリアにとって異動がどんな価値になるのか、
対話を重ねることで理解・納得が深まると考えています。
特に転居を伴う異動の際には、できる限り前の段階からその可能性を伝えておく配慮や、
経済的な負担に対する支援も大事だと考え、この4月から拡充を図っています。
キャリア志向の高い社員をどうマネジメントしていく?
長崎:異動の話を聞いて思うのは、組織主導のレールに乗らない自律的なキャリア観を持つ人が
増えつつある時代になったということです。
新入職員採用の際にもそれは感じているのですが、内定の時点で、今後どんな仕事ができるのかを明示しないと
辞退されてしまうことがあるのです。
なので今は、希望の職種のイメージや将来のキャリア、本人の不安などを面接で確認し、
本人の希望に沿った配属を行っています。
望むキャリアを積める確約がないと、人材が離れてしまうケースもあります。

森田:若手に限らず、どの年代においても個々のキャリアに対する考え方は変わってきていますね。
そこに丁寧に寄り添うために、弊社では、各部署ごとにキャリアマネジメント専門の担当者を設けています。
部長がチームマネジメントとプロジェクトマネジメント、キャリアマネジメントのすべてを担うには限界があるので、
それらを分業化して3人の担当が部署を見る、三位一体制を導入しています。
仕事柄、技術者が多いので、キャリアマネジメントの担当者は、その職種に長けた社員であることも必須条件です。
ただ人事部がかかわるのではなく、自分の専門にする技術に長けた上司がキャリアの相談に乗ってくれる方が、
やはり社員にも響くはずです。
弊社が大事にしているのは「人こそ資本」という考え方。
人材がすべての資本になるからこそ、育成は特に力を注ぐべき課題です。
山田: 弊社もキャリア育成には力を入れています。
人材戦略を経営戦略の一つとして位置付け、この4月からは社員のキャリア形成を促すキャリアデザイン部を創設し、
さまざまな取り組みを行っていますが、社員が他社に出向してまったく違う仕事に従事する「越境学習」もそのひとつです。
出向先はさまざまで、例えば、社員が千葉県松戸市で中学校の教員を務めるプログラムも。
そこでの体験を通じて、元々持っていたスキルを活かしながら、新たな能力の向上につなげていくことが狙いです。
加えて、風土の違う職場で働く社員が交わることは、出向先にとってもメリットがあるようです。
松戸市の中学校へは、はじめは2名の社員を出向させていましたが、今年は5名に増やしてほしいという要望をいただきました。
異業種間の交流は、よい意味での摩擦を生み、互いの組織の成長にもつながると実感しています。
60代の社員にも活躍できる場を作る
長崎: ただ、キャリアに自発的な職員がいる一方で、そうではない職員の存在にも目を向けなければならないですよね。
弊会も「キャリア自律」をテーマに職員向けの学習会を昨年から始めていますが、
「結局、それは若い職員の話だろう」と私自身も感じる部分がありました。
50代以降、年齢やキャリアを重ねる中で、なかなか意欲的になれず、
モチベーションを上げることに難しさを感じているという人も、多いのではないでしょうか?

山田:50代と言えばまさに私たちの世代ですが、昔と今ではキャリアの考え方がまるで変わりましたもんね。
ずっと会社主導でキャリアを形成されていた時代を過ごしてきて、
急に「キャリア自律」と言われても、やはりそこには難しい部分があるだろうと理解できます。
けれどそんな社員が、年齢にとらわれず活躍し続けられる環境を作ることもまた重要です。
弊社の現行制度では、60歳で役職定年となりますが、これの見直しを検討しています。
本人の意欲と会社の需要が合えば年齢にとらわれず、
自身が最も能力を発揮できる場で活躍していただきたいと考えています。
森田:弊社でも60歳を過ぎた社員が海外に派遣され、第一線で働いている例は多くあります。
年齢が上がるということは、経験やスキルをそれだけ積んでいるということ。
特に我々の業界では経験則が重視されるので、ベテランの存在は非常にありがたいものです。
他社への転職を考える前に自社をもっと知ってほしい
人手不足の話題もありましたが、キャリア志向のある社員ほど外に出ていく可能性もあります。
そこについてはどう考えていますか?
山田:人材に流動性があるのは、ある程度仕方のない部分もあると思っています。
実際、私たち自身もキャリア採用をたくさんしていて、今や社内でも中途採用者は800人を越すほどですから。
社内ではなかなか育てられないキャリアを持った人材がいるからこそ、できる仕事も確実にあります。
だから、会社を辞めることが必ずしもノーであるとは言えません。
それに、一度辞めても、別の場所で経験を積み、また戻ってきてもらうことだってあるかもしれませんし。
そのためにも、自社の魅力をもっと知ってもらう機会を作ることは大事ですね。
今、弊社では「ジョブフェスティバル」と題し、年に1回、大きな食堂に社員が集まり、
40近くある社内の全部署がそれぞれの仕事について話し、交流するイベントを開いています。
社内にも、まるで転職するような幅広いキャリアの選択肢があることを知ってもらいたいと思っての取り組みです。
長崎:
弊会でも組織内インターンシップの制度を今年からトライアルします。
考え方は同じで、自分の関心がある部署の業務を体験することで、自律的に将来のキャリアを考える機会としています。
組織内には生協ならではの多種多様な職務があり、おもしろい仕事がまだまだいっぱいあるんだよ、
ということを知ってもらうことが狙いです。
また、今の自分の仕事を見つめ直し、他部署との業務のつながりを感じることで、
働きがいの向上や協働する風土作りに繋がればと考えています。
まずは気軽に応募してみてほしいですね。
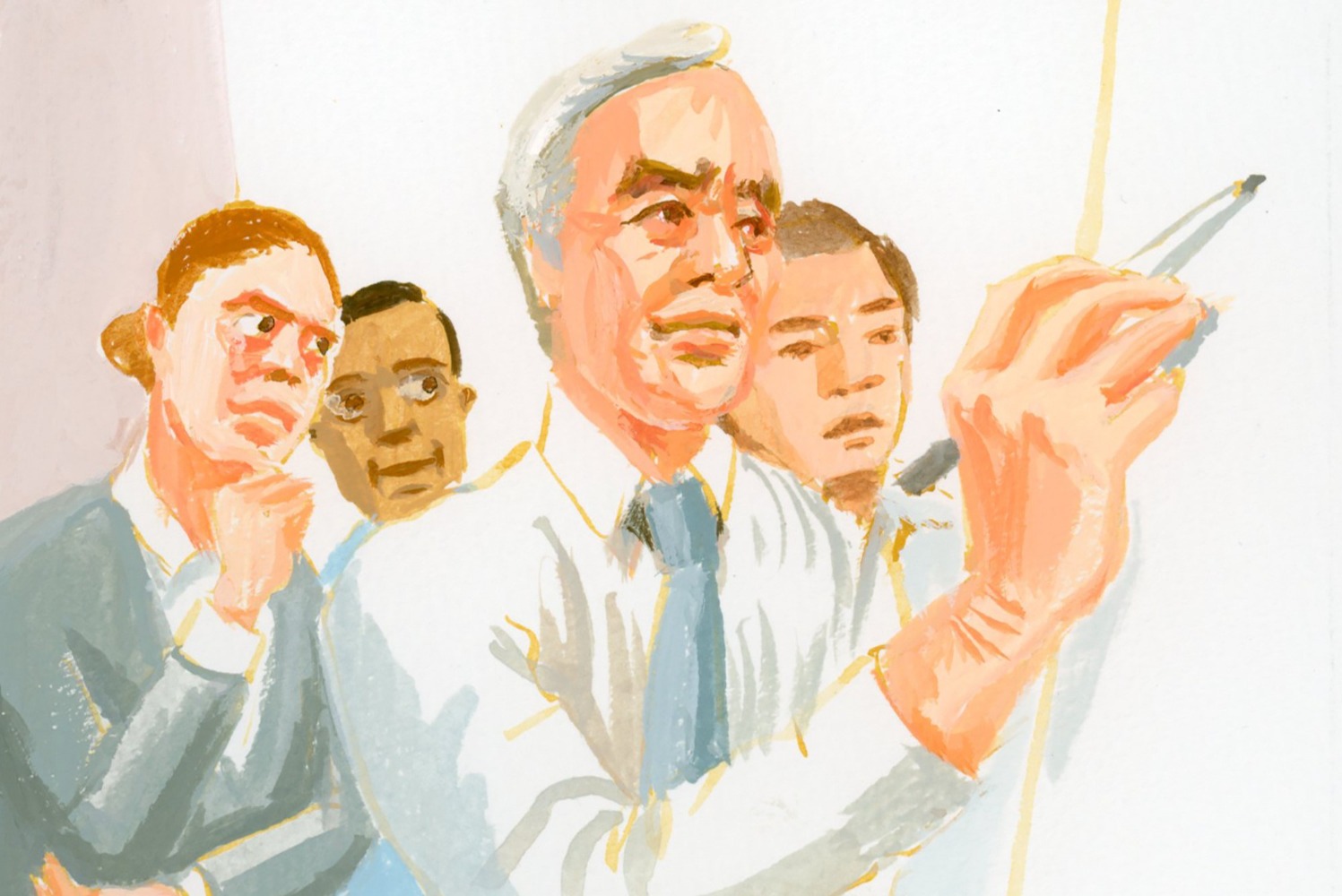
森田:シンプルですが、魅力的な仕事を創出していくことも課題です。
弊社では化学から機械、建築、電気、制御までいろいろな分野のエンジニアがかかわって、
チームでひとつの大きなプロジェクトを遂行することが基本で、
それくらい大きな仕事にかかわれる経験は、弊社ならではの魅力でもあると考えています。
かかわってよかったと思えるプロジェクトをデザインし、やりがいを作り出していくことが、
会社に人をつなぎとめる理由にもなります。
山田: 働き方改革をして、どんなに働きやすい環境が整っていても、
結局のところ「働きがい」がなければ社員は離れていってしまいますからね。
今現在だけでなく、ライフステージに合わせて、
例えば、子供が大きくなった段階で再び仕事の意欲が高まるような社員がいれば、
そのモチベーションに応える環境を常に用意できるようでありたいです。
1人じゃできないことがあるからサラリーマンはおもしろい
最後に、サラリーマンであるからこそ感じる「仕事のおもしろさ」を教えてください。
森田:昨年インドネシア駐在から帰ってきたのですが、
これまでの人生でサハラ砂漠、カタール、インドネシアなど、
世界の国々で数万人規模がかかわる建設プロジェクトに従事してきました。
この経験は、企業にいなければまずできません。
私は「組織を使う」というとらえ方でも構わないと思っていて、
チームでやるからこそのおもしろい仕事に携われるのは、やはりサラリーマンの特権だと感じます。
長崎:私は、いい意味で「雑多」なところが魅力だと思っています。
組織に属すれば、自分が好きな人だけと仕事をすることはできませんし、苦手な仕事だって回ってきます。
それは個人で仕事をする場合とは異なりますが、だからこそ、苦手だと思っていた人の意外な魅力に気づいたり、
自分では想像もしていなかった新しい世界が広がったりすることもあります。
例えば、私は福利厚生の一環として、お弁当注文などの昼食サービスの利用を担当していますが、
それも雑用と受け止めるか、社員の健康を支える「健康経営」の取り組みの一環と考えるかで、
おのずとモチベーションは変わってきますよね。
雑多な中から何を受け取り、吸収していくかに醍醐味があると思うんです。
自分の受け取り方次第で、組織で働く人たちももっと楽しめると思っています。
山田:会社にいるからこそ、いろいろな人に会えるおもしろさはありますね。
私自身も営業で20年、コーポレートで10年近く働いてきて、
大手から中小企業まで、本当にさまざまな方と出会う機会がありました。
営業時代は、顧客である経営層の方々と貴重なお話をすることができ、
今は人事・総務として役員や社員一人ひとりと対話をしていて、それらの出会いから得られたものが今の自分を作っています。
蓄えられた引き出しの数々を振り返ると、サラリーマンで良かったと思います。
会社に誇りを持ち、胸を張って会社のことを話せる社員が増えてくれたら、こんなに嬉しいことはありません。

メトロミニッツ2024年6月号 特集「サラリーマンっておもしろい」より転載
Text:KAORUKO SEYA(インスタグラム:@kaorukoseya)
Illustration:MARIKO OTA

社員の働きやすさを支援!
スターツが企業不動産の課題を解決
無料相談はこちらから
-
カテゴリ:
- 働くっておもしろい
-
タグ:
まずは、お気軽に今のお困りごとを
お聞かせください。
スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。
長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。