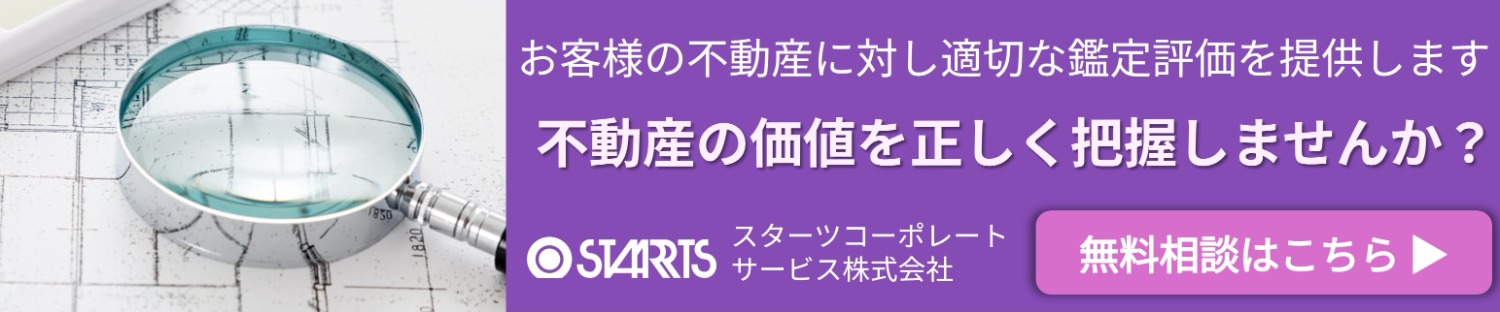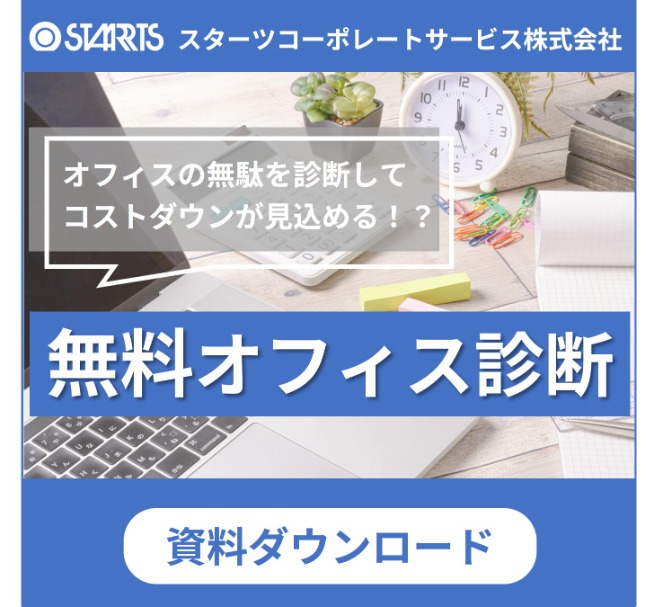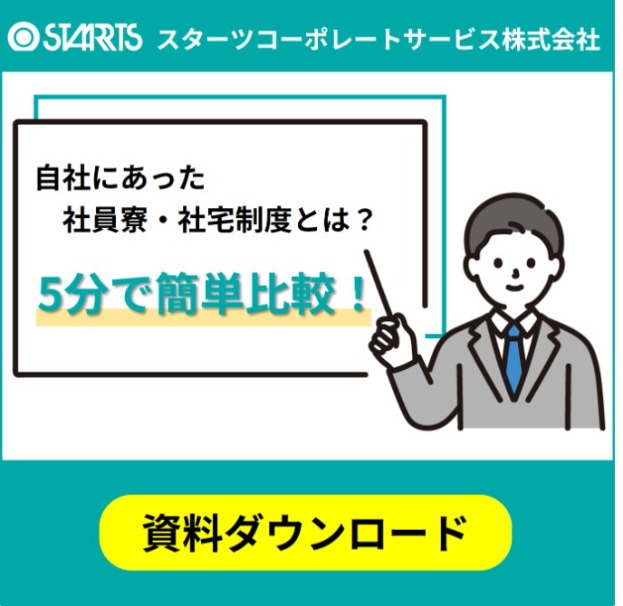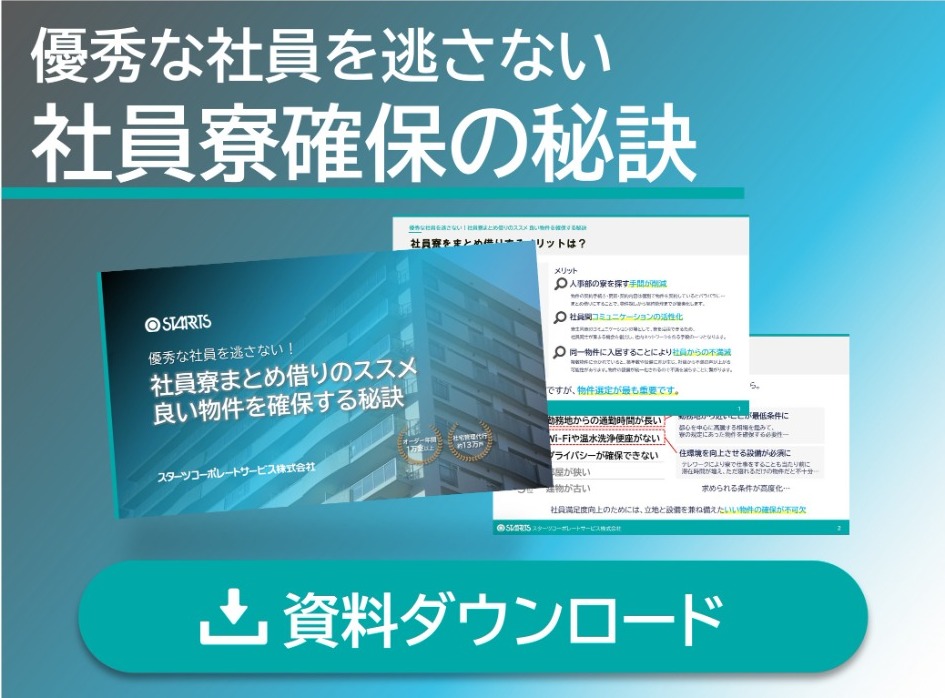企業が保有する不動産のハザードリスク -資産価値と事業継続性を守るために今できること-

企業が保有する不動産は、単なる資産ではなく、事業の基盤であり、企業価値を支える重要な経営資源です。
オフィスビル、物流拠点、工場、店舗、社宅など、用途は多岐にわたりますが、いずれも企業活動に欠かせないものです。
しかし、近年、地震・洪水・土砂災害・高潮・津波などの自然災害(ハザード)が頻発し、
企業の不動産資産に甚大な影響を及ぼすケースが増えています。
こうした災害リスクは、企業の資産価値や事業継続性に直結する問題であり、
従来の不動産管理の枠を超えた視点が求められています。
本稿では、企業が保有する不動産に潜むハザードリスクの実態と、それにどう向き合うべきかを解説します。
Contents
ハザードリスクの多様化と企業への影響

日本は世界有数の自然災害多発国です。
地震はもちろん、台風による豪雨や河川氾濫、土砂災害など、地域によって異なるハザードが存在します。
企業が保有する不動産がこうしたリスクに晒されている場合、以下のような影響が考えられます。
○ 建物の損壊や浸水による物理的損失
○ 事業停止による売上減少や信用低下
○ 従業員や顧客の安全確保の困難
○ 資産価値の低下や売却困難
○ 保険料の引き上げ
○ 金融機関による担保評価の減額
○ ESG (環境・社会・ガバナンス)評価への悪影響
特に、物流拠点や製造施設、データセンターなど、事業の根幹を担う施設が被災した場合、
企業活動全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
災害は突発的に発生するため、事前の備えがなければ、復旧に多大な時間とコストを要することになります。
ハザードマップとリスク評価の重要性

国土交通省や各自治体が公開している「ハザードマップ」は、地域ごとの災害リスクを可視化する有効なツールです。
企業はまず、自社が保有する不動産がどのようなハザードに該当するかを確認することが重要です。
例えば、以下のような項目をチェックすることで、リスクの全体像が見えてきます。
○ 土地が洪水浸水想定区域に含まれているか
○ 地震時の液状化リスクがあるか
○ 土砂災害警戒区域に該当しているか
○ 津波浸水想定区域に含まれているか
○ 高潮による浸水リスクがあるか
これらの情報は、自治体の防災情報サイトや国土交通省の「重ねるハザードマップ」などで確認できます。
さらに、地盤の強度や過去の災害履歴なども加味することで、より精緻なリスク評価が可能になります。
ハザードリスクと資産価値の関係

不動産の資産価値は、立地や建物の状態だけでなく、災害リスクによっても大きく左右されます。
たとえば、洪水リスクが高い地域では、保険料が高騰したり、金融機関の担保評価が下がることもあります。
また、ESG投資の観点からも、災害リスクへの対応は企業評価に影響を与える要素となっています。
さらに、近年では不動産取引時にハザード情報の開示が求められるケースも増えており、
企業が保有する不動産の「災害耐性」は、資産運用や売却戦略においても重要な判断材料となっています。
災害リスクを軽視したまま保有を続けることは、将来的な資産価値の毀損につながりかねません。
企業が取るべき対応策

ハザードリスクに対して、企業が取るべき対応は多岐にわたります。
以下はその一例です。
1. リスク評価の実施
専門家による不動産鑑定や災害リスク評価を受けることで、保有資産の脆弱性を把握できます。
地盤調査や建物の耐震診断なども含め、科学的根拠に基づいた評価が重要です。
2. BCP(事業継続計画)の見直し
災害時の代替拠点や復旧手順の整備は、事業の早期再開に不可欠です。
特に、複数拠点を持つ企業は、拠点間の連携やバックアップ体制の構築が求められます。
3. 保険の見直し
ハザードリスクに対応した補償内容の確認と更新は、万が一の際の損失軽減に直結します。
保険会社との協議を通じて、補償範囲や免責条件を明確にしておくことが重要です。
4. 施設の改修・移転検討
耐震補強や浸水対策、リスクの低い地域への移転など、物理的な対応も有効です。
特に老朽化した建物は、災害時の被害が大きくなる傾向があるため、早期の対応が望まれます。
5. 従業員への教育・訓練
避難訓練や災害時の対応マニュアルの整備は、人的被害の防止に直結します。
災害時の連絡体制や安否確認方法も含め、定期的な見直しが必要です。
これらの対応は、単なるリスク回避にとどまらず、災害時の企業の回復力を高め、
ステークホルダーからの信頼を得るためにも不可欠です。
不動産鑑定士が担う“平時と有事”の橋渡し

企業の不動産戦略においては、収益性や利便性に加え、
災害リスクや環境変化への適応力といった「持続性」が重要な評価軸となっています。
こうした中で、不動産鑑定は、ハザードリスクを含めた土地や建物の経済価値を適正に評価し、
資産の健全性を可視化する役割を担っています。
一方で、不動産アドバイザリーは、ハザードリスクに関する情報をより多角的かつ詳細に分析し、
資産の脆弱性や事業継続性への影響を評価する専門的支援を提供します。
特に複数拠点を有する企業にとっては、どの資産を維持し、どこにリスクが潜んでいるのかを見極めることが、
経営判断の要となります。
不動産鑑定とアドバイザリーは、平時における資産の適正評価と、有事に備えたリスクマネジメントの両面から企業を支え、
より安全かつ効果的な不動産活用を支援しています。
災害時の住家被害認定調査と不動産鑑定士の社会的役割

筆者が所属する日本不動産鑑定士協会連合会では、平成28年4月14日に発生した熊本地震の被災地に、
会員の不動産鑑定士を派遣して以来、全国各地で毎年のように頻発する自然災害に際しても、被災地にいち早く会員を派遣し、
住家被害認定調査等の支援活動を継続して行ってきました。
自然災害の被災地においては、被災者は罹災証明書を速やかに取得し支援を受ける必要があるものの、
災害直後は人的・交通的制約により発行が遅延する場合があります。
日本不動産鑑定士協会連合会は、自治体等の要請を受けて全国の不動産鑑定士を被災地に派遣し、家屋調査を実施することで、
罹災証明書の迅速な発行に寄与しており、その社会的貢献は高く評価されています。
住家被害認定調査とは、地震や風水害等の災害により被災した住宅の被害程度を認定するための調査であり、
この認定結果に基づいて、被災者の方々に「罹災証明書」が発行されます。
「罹災証明書」は、被災者生活再建支援金等の各種支援制度を受けるために必要な証明書です。
令和6年1月1日、能登半島地震が発生し、各地に甚大な被害をもたらしました。
石川県からの支援要請を受け、日本不動産鑑定士協会連合会は不動産鑑定士を派遣し、
住家被害認定調査等の支援活動を行いました。
この支援活動は、複数の自治体に対して切れ目ない支援を行うため、全国の不動産鑑定士に参加を呼びかけ、
延べ1,564人(実人数262人)が参加する全国規模での連携体制の取り組みとなりました。
令和6年1月から9月にかけて、石川県輪島市、珠洲市、七尾市、かほく市、志賀町、内灘町、穴水町で支援活動を行いました。
筆者も、石川県珠洲市における住家被害認定調査に参加しました。
また、平時には、実際の建物を用いて、被害状況を想定した実地演習を、発災後の現地で活動をしたことがない自治体職員や不動産鑑定士を対象に実施しており、筆者も運営側として参加しています。
発災時の住家被害認定調査を円滑に実施するためには、平時から実地演習を通じて多くの調査関係者が有事に備えることが重要です。これにより、次にいつ発生するかわからない大災害に際しても、迅速な被災者支援が可能となります。
日本不動産鑑定士協会連合会や東京都不動産鑑定士協会は、精力的にこのような活動を行っています。
こうした取り組みが、被災者の早期の生活再建に少しでも寄与できれば幸いです。


この画像は、筆者が令和6年8月に石川県珠洲市正院町で撮影したものです。
現地では、著しく損壊した建物が多数、確認されました。
未来の備えとしての「不動産鑑定・アドバイザリー」

災害時の支援活動を通じて、不動産鑑定士は現場対応力と専門性を発揮してきましたが、
こうした知見は平時の資産管理にも活かすことができます。
特に、災害リスクを含む不動産の脆弱性評価は、企業の資産戦略やBCP策定において重要な視点となります。
次に紹介するような不動産鑑定・不動産アドバイザリーの活用は、将来の備えとしても有効です。
不動産鑑定士によるリスク評価は、資産価値の見直しや保有方針の判断に役立ちます。
災害リスクを加味した鑑定は、企業の資産戦略において極めて有益です。
また、不動産アドバイザリーは、災害リスクを踏まえた施設の再配置やBCP支援、保険戦略の立案など、
実務的なサポートを提供します。不動産鑑定に比べて、より多角的なリスク評価が可能です。
まとめ

ハザードリスクは、目に見えない不動産の「弱点」であり、放置すれば企業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
だからこそ、専門的な視点からの評価と戦略的な対応が求められます。
企業が保有する不動産の「見えないリスク」を可視化し、未来に向けた資産戦略を描くために、
今こそ、不動産鑑定・不動産アドバイザリーで資産の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
Writer's Profile

- 執筆者
-
スターツコーポレートサービス株式会社
中川 貴雄(なかがわ たかお)
経歴-
2007年3月近畿大学大学院総合理工学研究科修士課程修了。
同年4月スターツグループ入社。企業向けの不動産投資、売却のアドバイザリーに従事し、2020年9月に不動産鑑定士に登録。
2023年7月 東京都不動産鑑定士協会 災害支援対策委員・総務財務委員に、
2024年4月 東京都不動産鑑定士協会の推薦を受け、東京都武蔵野市の固定資産評価審査委員会委員に就任。
不動産のプロとして、数多くの企業の資産コンサルティングを手掛けている。
不動産鑑定士
-
カテゴリ:
- 企業不動産戦略
-
タグ:
まずは、お気軽に今のお困りごとを
お聞かせください。
スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。
長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。