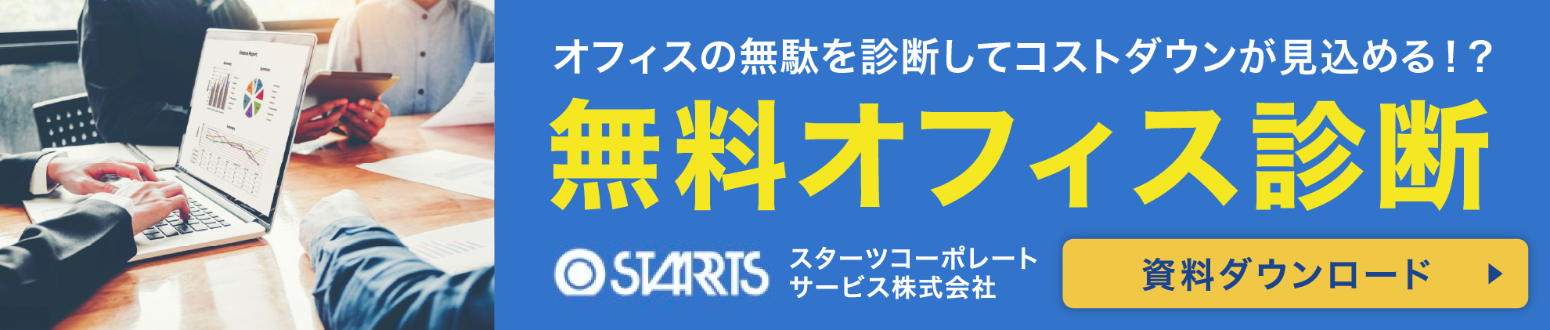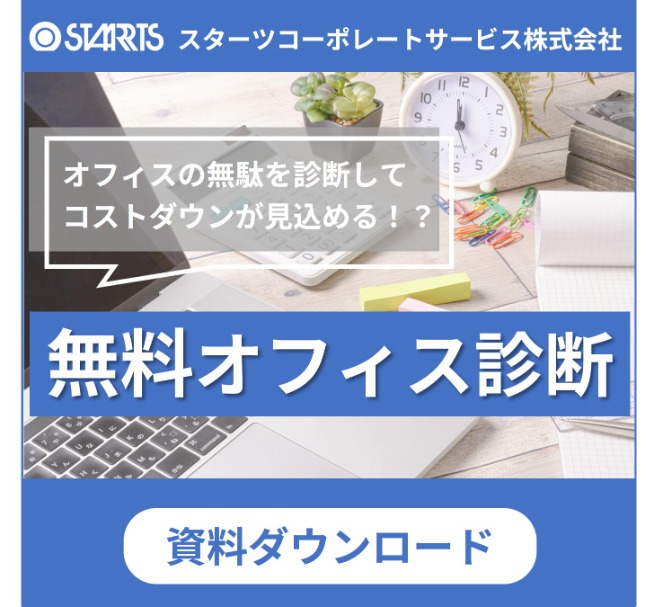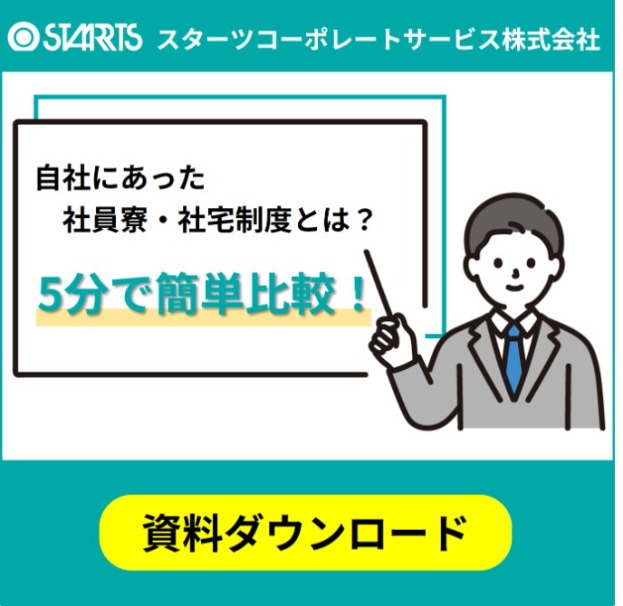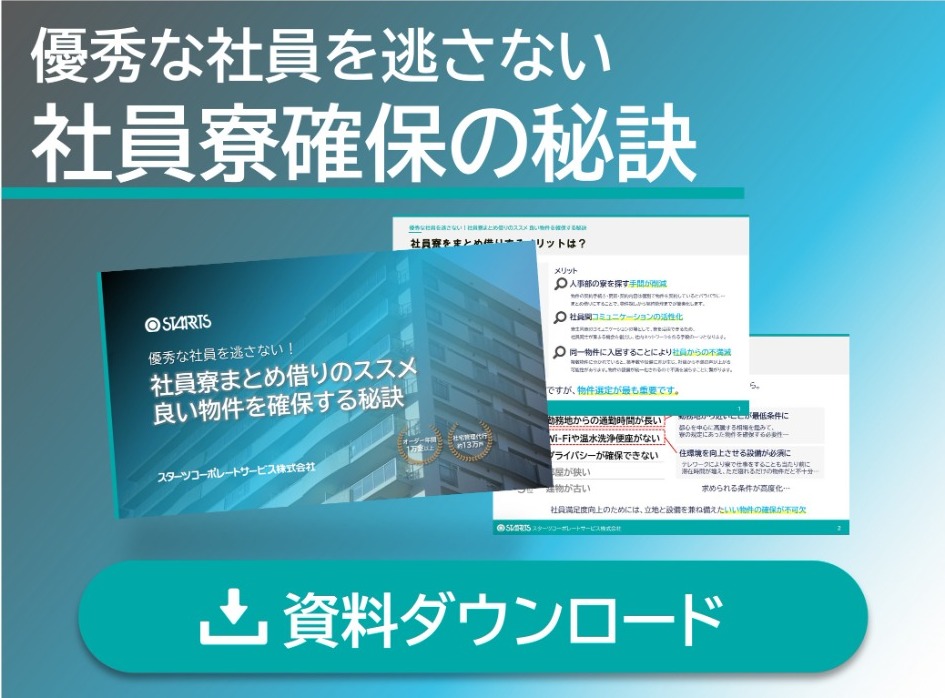BCPとは?わかりやすく意味や目的、策定方法を解説

あなたは、BCPという言葉を聞いたことがありますか?
BCPとは、災害などの危機的な状況における企業や団体の事業継続計画のことです。
BCPは、事業資産の損害を最小限に抑え、重要な業務を継続し早期復旧を図ることで、
企業価値や社会的信頼を維持することを目的としています。
しかし、BCPは単に災害対策ではありません。
BCPは、事業の継続に必要な戦略や計画を具体的に示すものです。
では、BCPはどのように策定するのでしょうか?
この記事では、BCPの意味や目的、策定方法をわかりやすく解説します。
Contents
BCPの意味と目的

BCPとは何か
BCPは、Business Continuity Plan(事業継続計画)の略称です。
BCPとは、自然災害やテロ、システム障害など危機的な状況に遭遇した時に、
事業資産の損害を最小限に抑え、重要な業務を継続し早期復旧を図ることが大切です。
●事業資産
事業資産とは、企業や団体が事業を行うために必要なもので、
人(従業員や顧客)、物(商品や設備)、金(売上や資金)、情報(データやノウハウ)などがあります。
これらの事業資産が危機的な状況で失われたり損傷したりすると、事業に大きな影響が出ます。
●重要な業務
重要な業務とは、危機発生時にも必ず継続しなければならない業務や、中断した場合に大きな損失や被害が生じる業務です。
例えば、医療機関の場合は救急医療や入院管理、銀行の場合は預金引き出しや送金サービスなどがあります。
これらの重要な業務を継続しなければ、顧客のニーズに応えることができません。
BCPの目的は何か
BCPの目的は、単なる防災対策と異なり、
目的を「事業の継続」に明確に置いて、具体的な行動指針を示しています。
緊急時にも事業を途切れずに継続し、途切れたとしても早期の復旧を実現できれば、顧客の信用を維持することが可能です。
株主や市場からも高評価を得て、それが企業価値の維持と向上につながり、社会的な信頼を得ることもできます。
特に日本では、2011年の東日本大震災をきっかけにBCPの重要性がますます注目されています。
内閣府では、2005年公表の「事業継続ガイドライン」でBCP策定を強く推奨しており、
2023年に改訂された最新版が公式サイトからダウンロードできます。
参考:事業継続ガイドライン(令和5年3月)
BCPをわかりやすく理解する
BCPの基本的な構成要素
BCPを理解するうえで重要なのは、計画の構成要素です。
一般的には、リスクの特定、影響度の評価、優先業務の明確化、代替手段や復旧手順の策定、訓練・検証・見直し、
というプロセスが含まれます。
これらを体系的に整理することで、企業は災害時にどの業務を優先的に復旧させるべきか、どの手段を用いて復旧するかを
明確にできます。わかりやすくまとめると、BCPは「事前準備の設計図」とも言えます。
災害やトラブルへの備えの重要性
BCPが求められる理由は、自然災害、停電、システム障害、パンデミックなど、事業活動を妨げるリスクが多岐にわたるからです。
これらのリスクに対応するため、企業は業務の優先順位を決め、最小限の資源で迅速に復旧できる体制を整える必要があります。
わかりやすく言えば、BCPは「業務を止めないための安全網」としての役割を持ちます。
計画の策定と運用のポイント
BCPの策定において重要なのは、計画を作るだけで終わらず、実際に運用可能な状態にしておくことです。
具体的には、連絡体制の整備、代替拠点の準備、情報システムのバックアップ、社員教育や訓練などが挙げられます。
また、BCPは固定的なものではなく、定期的に見直しを行い、変化するリスクや業務環境に対応させることが重要です。
わかりやすく言えば、BCPは「常に更新される非常時対応のマニュアル」と考えると理解しやすいでしょう。
社員への浸透と理解の重要性
BCPの効果は、計画を策定するだけでは不十分です。
社員一人ひとりがBCPの内容を理解し、自分の役割や対応手順を把握していることが不可欠です。
研修や訓練を通じて、全社員が緊急時に何をすべきか明確に理解することで、混乱を最小限に抑え、事業継続性を確保できます。
わかりやすく言えば、BCPは「社員全員で運用する安全計画」と捉えることができます。
BCPの基本的な考え方

なぜBCPが必要なのか
企業活動は、自然災害や事故、サイバー攻撃など、さまざまなリスクにさらされています。
これらのリスクが顕在化した場合、業務の停止や情報漏えい、取引先への影響など、多方面に影響が及ぶ可能性があります。
BCPは、こうした事態を想定して業務の優先順位や復旧手順を整理し、被害を最小化するための指針となります。
BCPの構成要素
BCPを構築する際には、いくつかの重要な要素があります。
まず、重要業務の特定です。企業活動の中で中断が許されない業務や取引先に影響を与える業務を明確にします。
次に、リスク分析と対応策の策定です。
自然災害や停電、情報システム障害など、発生が予想されるリスクを洗い出し、それぞれに対する対応手順を整備します。
また、社員や関係者への情報共有手段も計画に含める必要があります。
長期的な事業安定のために
BCPは単なる危機管理のツールではなく、長期的な企業の安定と成長を支える制度です。
事前にリスクを想定し、適切な対策を整えることで、企業は予期せぬ事態にも強い体制を持つことができます。
これにより、従業員や取引先からの信頼を維持し、事業を継続させる力を高めることが可能です。
BCPとBCMの違いとは?

BCP(事業継続計画)とよく比較される概念にBCM(事業継続マネジメント)があります。
どちらも企業のリスク対策として重要ですが、目的や範囲、実施方法に違いがあります。
BCPは特定の災害や障害が発生した際に、事業をどのように継続・復旧させるかを計画するものです。
一方で、BCMはそのBCPを含め、組織全体で事業継続のための管理体制を確立し、維持・改善するための包括的な枠組みを指します。
BCPは計画、BCMは管理
BCPは企業が災害やシステム障害などの緊急事態に直面したときに、どのような手順で重要業務を継続するのかを具体的に定めた計画です。
たとえば、地震発生時の従業員の避難ルートや、サーバーダウン時のデータ復旧手順などが含まれます。
一方で、BCMはBCPを適切に運用し、組織全体として事業継続に関する意識を高めるための管理システムです。
定期的な訓練や教育、評価・改善を行うことで、組織の事業継続能力を維持・向上させることを目的としています。
BCPは短期的な対応、BCMは長期的な視点
BCPは、危機発生時の短期的な対応策に焦点を当てています。
たとえば、台風や地震でオフィスが使えなくなった場合に、どこで業務を継続するのか、どのように取引先と連絡を取るのかといった具体的な対応が含まれます。
一方で、BCMは企業が長期的に安定した事業運営を続けるためのフレームワークです。
定期的にリスク評価を行い、想定される脅威に備えるための戦略を立てることが求められます。
BCMの一環としてBCPの見直しを行い、実際の運用状況を踏まえて計画を改善するプロセスも含まれます。
BCPは一部門の責任、BCMは全社的な取り組み
BCPは特定の事業部門や業務単位で策定されることが多く、それぞれの部門が担当する範囲を明確にし、必要な対策を講じることが求められます。
たとえば、IT部門ではサーバー障害時の復旧手順、物流部門では輸送経路の代替策などが策定されます。
対して、BCMは企業全体の経営戦略の一部として位置づけられ、経営層が主導し組織全体で取り組む必要があります。
経営陣が災害対策の方針を決定し、それをもとに各部門が個別のBCPを策定することで、企業全体として統一された対応が可能となります。
BCPは実践的な対応、BCMは継続的な改善
BCPは具体的な事業継続手順を記した計画であり、いざという時にすぐに実行できる形になっていることが重要です。
計画には、緊急連絡先の一覧、バックアップデータの保存場所、災害時の指揮系統などが明確に記載されます。
一方で、BCMは組織が継続的に改善を行い、事業継続の能力を高めるためのプロセスです。
たとえば、定期的なBCP訓練の実施、従業員向けの教育プログラム、発生した危機への対応の振り返りといった活動が含まれます。
BCMが機能することで、BCPは実効性を持ち、必要に応じて最適化されていきます。
わかりやすく理解するためのBCP用語解説

BCP(事業継続計画)は企業や組織が災害や事故などの緊急事態に対応し、重要な業務を中断させずに継続するための計画です。
初めてBCPを学ぶ人にとっては専門用語が多く、理解が難しい場合もあります。
ここでは「bcp とは わかりやすく」と検索している人に向けて、理解するために、BCPに関連する基本的な用語を解説します。
リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、組織が直面する可能性のあるリスクを特定し、その影響や発生確率を評価するプロセスです。
BCP策定の初期段階で行い、どのような危機に備えるべきかを明確にします。
重要業務(クリティカルビジネスプロセス)
重要業務とは、企業の存続や収益に直結する業務のことを指します。
BCPでは、これらの業務を優先的に継続するための戦略を立てます。
例えば、製造業であれば生産ラインの維持、サービス業であれば顧客対応業務が該当します。
リカバリータイム目標(RTO)
RTO(Recovery Time Objective)は、災害発生後に業務を復旧させるまでの許容時間を示す指標です。
例えば、RTOが24時間の場合、災害発生後24時間以内に業務を再開することが目標となります。
リカバリーポイント目標(RPO)
RPO(Recovery Point Objective)は、データ復旧において許容される最大のデータ損失時間を示します。
例えば、RPOが1時間であれば、1時間前までのデータは復元可能であることが求められます。
危機管理(クライシスマネジメント)
危機管理は、突発的な重大事故や災害が発生した際の対応策や組織の意思決定を行う体制を指します。
BCPと連携し、初動対応や被害拡大防止に注力します。
事業影響度分析(BIA)
BIA(Business Impact Analysis)は、災害発生時に各業務がどの程度組織に影響を与えるかを分析する手法です。
これにより、優先すべき業務や資源配分を明確にします。
BCP策定方法

ここからBCP策定方法を「5つのSTEP」でわかりやすく解説していきます。
STEP1:BCP策定の目的設定
まず、企業や団体がどんな危機に対応するか、どんな事業を優先するか、どんなリスクを回避するかなど、
BCP策定の目的や方針を明確にします。
この段階では、経営層や関係者の合意形成が重要です。
●危機
危機とは、企業や団体にとって大きな影響を与えるような事態のことです。
例えば、地震や津波、火災や水害、テロや暴動、システム障害やサイバー攻撃などがあります。
これらの危機に対して、どのように対応するかを考えます。
●事業
事業とは、企業や団体が行っているすべての業務のことです。
例えば、製品やサービスの開発や販売、顧客対応やアフターサービス、経理や人事などがあります。
これらの事業の中から、重要度や影響度に応じて優先順位をつけます。
●リスク
リスクとは、危機が発生した場合に生じる可能性のある損失や被害のことです。
例えば、人命や財産の損失、売上や利益の減少、信用や評判の低下などがあります。
これらのリスクを回避するために、どのような対策を取るかを考えます。
STEP2:重要業務の分析
次に、企業や団体が行っているすべての業務を洗い出し、その中から重要度や影響度に応じて優先順位をつけます。
●重要業務
重要業務とは、危機発生時にも必ず継続しなければならない業務や、中断した場合に大きな損失や被害が生じる業務です。
重要業務の分析には、「ビジネスインパクト分析(BIA)」という手法がよく用いられます。
●ビジネスインパクト分析(BIA)
ビジネスインパクト分析(BIA)とは、各業務が危機発生時にどれだけ影響を受けるかを定量的に評価することです。
例えば、「最大許容停止時間(MTPD)」という指標で、各業務が停止できる最大時間を決めます。
また、「復旧優先度(RTO)」という指標で、各業務が復旧すべき順番を決めます。
これらの指標をもとに、重要業務を抽出します。
STEP3:直面する危機シナリオの想定
さらに、企業や団体が直面する可能性のある危機シナリオを想定します。
危機シナリオとは、「何が起こるか」「どんな影響があるか」「どう対処するか」などを具体的に記述したものです。
危機シナリオの想定には、「リスク分析」や「リスク評価」などの手法がよく用いられます。
●リスク分析
リスク分析とは、危機が発生する確率とその影響度を評価することです。
例えば、「地震発生確率×地震規模×地震被害」という式で、地震リスクを算出します。
また、「テロ発生確率×テロ規模×テロ被害」という式で、テロリスクを算出することができます。
これらのリスクをもとに、危機シナリオを作成しなければなりません。
●リスク評価
リスク評価とは、危機シナリオに対する対策の効果やコストを評価することです。
例えば、「対策費用×対策効果」という式で、対策の費用対効果を算出します。
また、「対策優先度=対策効果÷対策費用」という式で、対策の優先度を決めます。
これらの評価をもとに、最適な対策を選択します。
STEP4:事業継続戦略の策定
そして、重要業務を継続するために必要な人員、資材、設備、情報システムなどのリソースを確保する方法を考えます。
これが事業継続戦略です。
事業継続戦略には、「代替拠点の確保」「代替手段の導入」「代替ルートの確保」「代替サプライヤーの確保」などがあります。
●代替拠点の確保
代替拠点の確保とは、危機発生時に本社や工場などが使用できなくなった場合に、
別の場所で業務を継続することです。
例えば、他の支社や営業所、ホテルや学校などがあります。
代替拠点には、必要な設備や通信回線などが整っていることが望ましいです。
●代替手段の導入
代替手段の導入とは、危機発生時に通常使用している機器やシステムなどが使用できなくなった場合に、
別の機器やシステムなどで業務を継続することです。
例えば、電話やファックス、メールやインターネットなどがあります。
代替手段には、互換性やセキュリティなどが確保されていることが望ましいです。
●代替ルートの確保
代替ルートの確保とは、危機発生時に通常使用している交通手段や配送経路などが使用できなくなった場合に、
別の交通手段や配送経路などで業務を継続することです。
例えば、電車やバス、自動車や自転車、航空機や船舶などがあります。
代替ルートには、安全性や速度などが確保されていることが望ましいです。
●代替サプライヤーの確保
代替サプライヤーの確保とは、危機発生時に通常使用している仕入先や取引先などが使用できなくなった場合に、
別の仕入先や取引先などで業務を継続することです。
例えば、原材料や部品、製品やサービスなどがあります。
代替サプライヤーには、品質や価格などが確保されていることが望ましいです。
STEP5:事業継続計画の作成
最後に、事業継続戦略を実行するための具体的な手順や役割分担をまとめた文書を作成します。
これが事業継続計画です。
事業継続計画には、「事前準備」「初動対応」「復旧対応」「復旧後対応」などのフェーズに分けて記述します。
●事前準備
事前準備とは、危機発生前に行うべき準備のことです。
例えば、代替拠点や代替手段などの確保や契約、重要業務やリソースの洗い出しや整理、
危機管理組織や連絡体制の構築、教育や訓練などがあります。
事前準備には、定期的な見直しや更新が必要です。
●初動対応
初動対応とは、危機発生時に行うべき対応のことです。
例えば、危機の発生や規模の確認、危機管理組織や関係者への連絡、重要業務の停止や移行、人命救助や安否確認などがあります。
初動対応には、迅速かつ正確な判断と行動が必要です。
●復旧対応
復旧対応とは、危機発生後に行うべき対応のことです。
例えば、重要業務の再開や復元、事業資産の回復や再建、顧客や株主への情報提供や謝罪などがあります。
復旧対応には、段階的かつ計画的な実施と評価が必要です。
●復旧後対応
復旧後対応とは、危機発生から完全に復旧するまでに行うべき対応のことです。
例えば、危機発生原因の分析や改善策の立案、事業継続計画の見直しや改善などがあります。
復旧後対応には、反省と学習が必要です。
BCPをわかりやすくまとめると
BCP(事業継続計画)は、企業が災害や事故といった非常事態に直面した際、
重要な業務を止めることなく、できる限り早く復旧するために策定する計画です。
企業が災害時に事業を維持できるかどうかは、その後の顧客や株主、取引先からの信頼に大きく影響を与えるため、
BCPは非常に重要な役割を果たします。
まず、BCPの目的は、企業の財産である「人」「物」「金」「情報」を保護し、できる限り早く通常の業務に戻ることです。
これにより、企業は災害などのリスクからの影響を最小限に抑え、長期的な損害を避けることができます。
企業価値を維持するためにも、BCPの策定は欠かせません。
次に、BCPを策定するためには、以下のステップが必要です。
まず、どのような危機が想定されるのかを分析し、次にその危機に対してどの業務が最も重要であるかを決定します。
例えば、医療機関では救急対応が優先され、銀行では預金管理や送金システムの維持が最優先事項となります。
さらに、事業の中で特に重要な業務に必要な人材、設備、情報システムなどを確保する計画を立て、
最後にそれらの実行手順をまとめます。
実際、多くの企業がBCPを策定し、災害やシステム障害に備えています。
たとえば、日本の銀行業界では、システム障害が発生しても重要な送金や取引サービスをすぐに再開できるよう、
複数のバックアップシステムを用意しています。
また、製造業においても、主要な部品を別の地域に保管しておくことで、
災害時にも速やかに生産ラインを復旧できるような準備が進められています。
このように、事前に綿密な準備を行うことで、非常時における事業の継続性を確保しています。
さらに、BCPを策定することで、企業はさまざまなリスクに対して迅速に対応する力を持つことができます。
たとえば、地震や台風といった自然災害だけでなく、サイバー攻撃やシステム障害にも備えることができるのです。
このような多様なリスクに対して事前に対応策を考えることが、企業の信頼性を高め、将来的な成長にもつながります。
計画の実施訓練を行うことで、緊急時の対応力もさらに向上します。
まとめると、BCPは企業が非常事態に対応し、事業を継続させるための具体的な手段を提供します。
これにより、顧客や株主の信頼を守り、社会的な評価を維持することができます。
企業が安定した事業運営を続けるためには、BCPを策定し、定期的に見直すことが非常に重要です。
この記事では、BCPの意味や目的、策定方法をわかりやすく解説しました。
特に、人・物・金・情報が揃うオフィスにおけるBCPの策定は不可欠です。
ぜひこの記事と下記からダウンロードできる資料を参考にBCPについて考えてみてください。
Operating Company
- 執筆者
-
スターツコーポレートサービス株式会社 COPPO!編集部
当社の特徴-
①法人さまごとの専任体制でお客様の課題をワンストップで解決
②社宅代行約450社・約13万件、継続25年以上、寮・社宅のプロ
③80社を超えるグループ会社と国内約3000社の提携不動産会社、
海外では21カ国・30拠点以上の日経不動産会社最大級のネットワーク
法人向け不動産サービスを中心に、スターツグループのコンテンツと
独自のネットワークを最大限活用し、様々な経営課題を共に解決します
当社のサービス:社宅代行・社員寮紹介、オフィス移転、不動産売買
-
カテゴリ:
- オフィス改善のコツ
-
タグ:
まずは、お気軽に今のお困りごとを
お聞かせください。
スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。
長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。