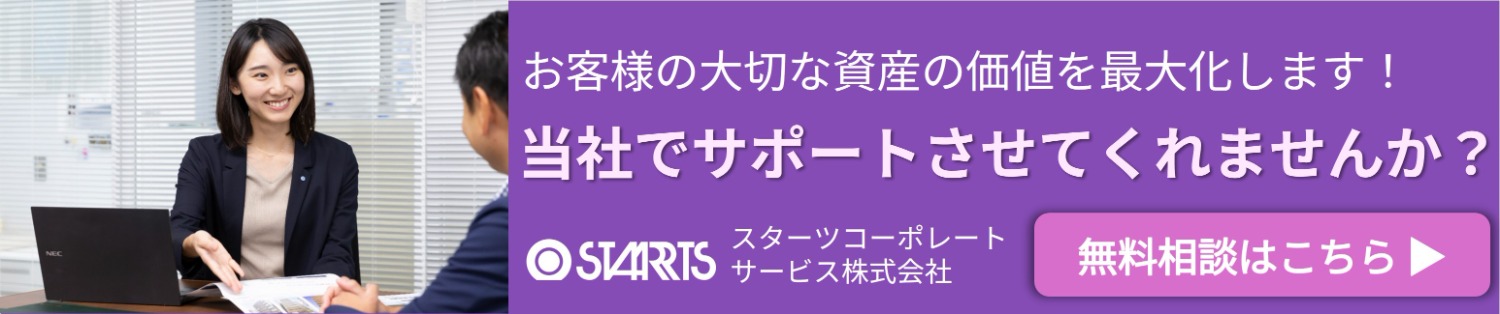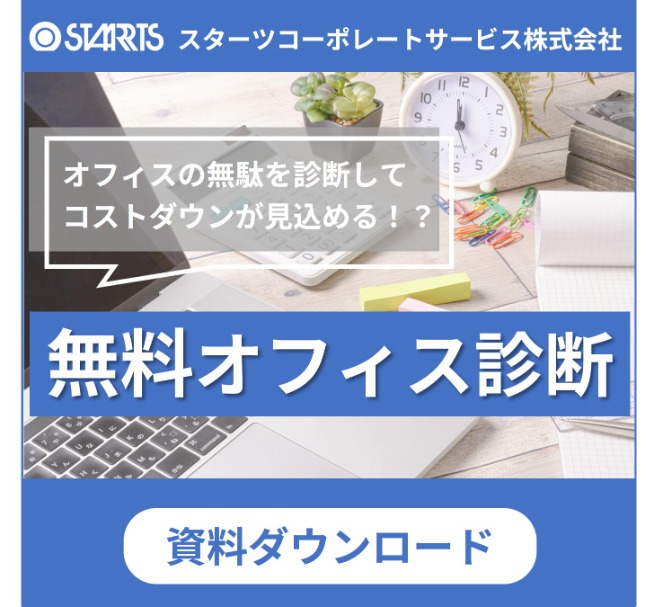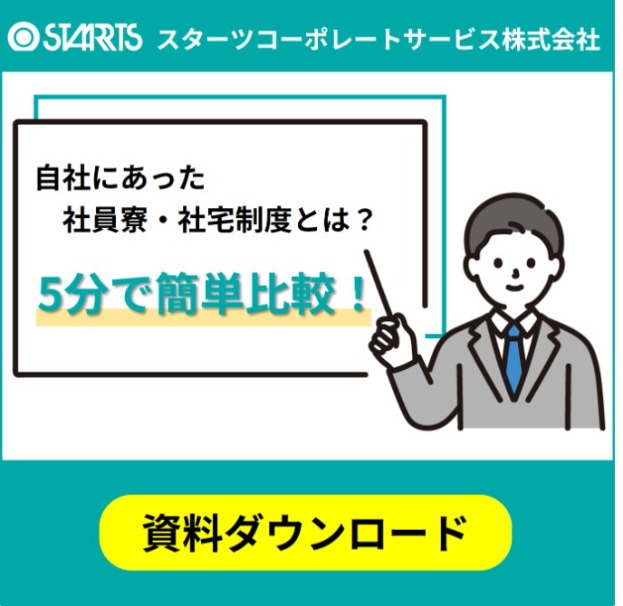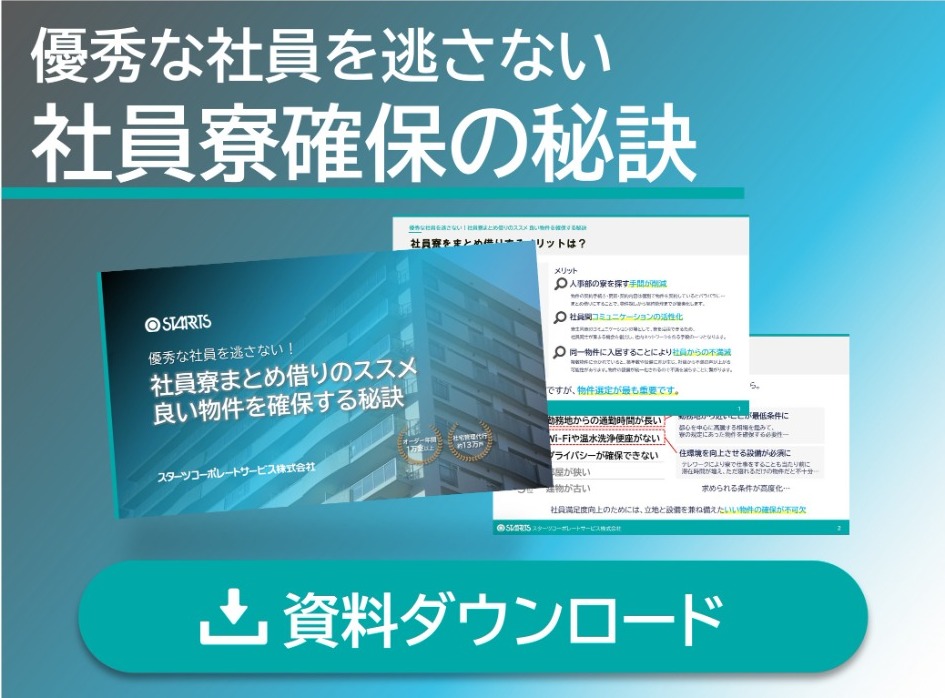不動産評価額とは?評価額の種類と調べ方を解説

所有する不動産の価値を調べる際、「不動産評価額」が用いられます。
不動産評価額には複数の種類があり、目的に応じた評価額を算出しなければなりません。
この記事では、不動産評価額の概要と種類、それぞれの評価額の調べ方について解説します。
所有する不動産の価値を調べたい方は参考にしてみてください。
不動産の評価額とは

不動産評価額とは、土地や建物など不動産の市場価値を示す指標のひとつです。
評価額は不動産売買や相続、資産評価など、さまざまな場面で重要な役割を果たします。
評価額はさまざまな方法で算出し、一般的には不動産鑑定士による鑑定や不動産業者の査定によって評価されますが、
自分で評価額を算出することも可能です。
しかし、不動産の評価額は土地の立地条件、面積、建物の構造や状態、周辺環境などに影響されます。
不動産評価額の種類と概要

不動産評価額には、用途や算出方法の異なる5つの種類があります。
ここでは、不動産評価額の種類とそれぞれの概要を解説します。
(1)固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する際に用いられる価格です。
所有する土地と建物の両方に設定されており、それぞれに固定資産税が課せられます。
不動産の評価額を確認するための指標とされており、とくに不動産の売却時に用いられることが多いです。
(2)公示地価
国土交通省が1年に1回公示する、全国26,000箇所ある標準地の1平米あたりの地価です。
公示地価とは、日本において毎年公表される土地の相場価格(地価)のことです。
年に1回、国土交通省によって公示されており、
全国26,000箇所ある標準地の1平米あたりの地価を知ることができます。
固定資産税評価額や相続税路線価など、不動産に関するさまざまな評価額を正確に算定することが目的であり、
不動産の売買や相続などの取引において重要な基準になっています。
(3)基準地価
基準地価とは、地方自治体が毎年1回(7月1日)算出し、公示する土地の平均的な価格水準のことです。
基準地価は、特定の土地の市場価値を把握するための基準として使用されます。
公示地価と基準地価が同じ地点の場合のみ年に2回公示されるため、地価の変化をより詳しく知ることができます。
(4)相続税路線価
相続税路線価(路線価)とは、相続税や贈与税を算出する際に用いられる評価額です。
1㎡あたりの宅地の単価を指します。相続税路線価は国税庁が毎年公示しており、
相続・贈与によって土地を取得した際に公平な相続税の課税をすることが目的です。
(5)実勢価格
市場や地域の経済状況、不動産の需要などに応じて変動するのが特徴です。
実勢価格は公示地価や路線価とは異なり、直接的な市場取引のデータを基に算出されており、
国土交通省の「土地総合情報システム」にて確認することができます。
実勢価格は不動産の市場価値を正確に把握する上で重要な指標であり、
不動産の売買価格や賃料を決定する際に活用されています。
【種類別】不動産評価額の算出方法

5つの不動産評価額を解説しました。それぞれの評価額は、不動産鑑定士や不動産業者によって査定されるのが一般的です。
しかし、自分で調べることもできます。ここでは、種類別で不動産評価額の調べ方を解説します。
(1)固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、以下の方法で調べることができます。
●税通知書の確認
●固定資産評価証明書を入手する
●役所に問い合わせる
●固定資産課税台帳を確認する
●全国地価マップを確認する
もっとも手軽に調べる方法は、毎年4月~6月頃に郵送される固定資産税納税通知書を確認することです。
課税通知書には、土地と建物の評価額が記載されています。
また、納税通知書に同封されている「固定資産評価証明書」で不動産の価格を把握することは可能です。
(2)公示地価の調べ方
公示地価は、国土交通省の「標準地・基準値検索システム」で調べることが可能です。
地図上で所有する不動産がある都道府県名や市町村名を選択し、
対象を「地価公示のみ」、調査年を「最新調査年のみ」を選ぶと、最新の公示地価が表示されます。
注意点として、地価公示結果は完全同一住所が表示されるわけではありません。
その場合、「対象の不動産にもっとも似通った物件」もしくは「地図で確認する」を選択すると、公示地価がわかります。
(3)基準地価の調べ方
基準地価は公示地価と同様に、国土交通省の「標準地・基準値検索システム」で調べることができます。
地図上で所有する不動産がある都道府県名や市町村名を選択し、対象を「都道府県地価調査のみ」に設定します。
基準地価も完全同一住所が表示されるわけではありません。
その場合、「対象の不動産にもっとも近い住所」もしくは「地図で確認する」を選択すると、
基準地価を確認することができます。
(4)相続税路線価の調べ方
相続税路線価は、一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」、
もしくは、国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
全国地価マップでは、相続税路線価のほか、固定資産税路線価も確認することが可能です。
また、不動産を相続した際に発生する「相続税評価額」は、以下の計算式で算出することもできます。
路線価×土地の面積=相続税評価額
しかし、正確な相続税評価額は土地の形状や隣接する道路の数などさまざまな要素で変動します。
そのため、上記の計算式で算出した評価額は、あくまで「概算」として理解する必要があります。
(5)実勢価格の調べ方
実勢価格を調べる場合には、公示地価や基準地価と同じように国土交通省の「土地総合情報システム」で調べることができます。
土地情報総合システムのページから「不動産取引価格情報検索」へ進み、「物件の種類」と「不動産のある地域」を入力します。
検索条件に該当する不動産の評価額が一覧で表示されるため、
所有する不動産と条件が近いものを確認することでおおよその評価額がわかります。
しかし今までのデータと違い、建物の状態や売却理由、さらには取引がされた時期や売主の事情など
多くの要素が複雑に関係している価格になっているので、発表している価格はあくまでも一つの目安として、
参考程度に利用するのが無難です。
不動産評価額に影響を与える要因

ここまでお伝えしてきた通り、不動産の評価額は、多くの要因に左右されるため、
一概に「この物件はこういう価値だ」と断定することは難しいです。
ここでは、不動産評価額に影響を与える代表的な要因について、具体的に解説していきます。
交通アクセスと周辺施設の充実度
まず、交通アクセスが不動産評価額に与える影響は非常に大きいです。
物件がどれほど利便性の高い場所にあるか、例えば駅からの距離や主要な公共交通機関へのアクセス状況は、
不動産の価値を大きく左右します。
特に、徒歩圏内に駅やバス停がある物件は、高い需要があり、その分評価額も高くなる傾向があります。
さらに、周辺施設の充実度も重要です。ショッピングセンター、病院、学校、公園など、日常生活に必要な施設が近くにあると、
居住者にとっての利便性が向上し、不動産の評価額も高まります。
特に、子育て世代に人気のエリアでは、これらの施設の存在が大きな影響を及ぼします。
土地の形状や面積
土地の形状や面積も、不動産の評価額に影響します。
整形地(四角い土地など)は建物を建てやすく、評価額が高くなる傾向があります。
一方で、旗竿地(細い通路を経て接道する土地)や不整形な土地は、建築や利用のしにくさから評価が低くなりがちです。
また、土地の広さは当然のことながら評価額に直結します。
実際に、同じエリア内でも、整形地と不整形地では大きな価格差が生じることがあります。
このため、土地の形状や面積は購入時や売却時に十分考慮すべきポイントです。
建物の築年数と構造
次に、建物の築年数や構造です。一般的に、新築物件や築年数が浅い物件は評価額が高くなります。
これは、建物がまだ新しく、修繕やリフォームの必要性が少ないためです。
また、耐震性能や断熱性能など、最新の技術を取り入れた建物はさらに評価額が高くなることがあります。
一方、築年数が経過した物件や、古い建物は価値が下がることが多いです。
ただし、リノベーションを施した古い建物や、ヴィンテージ感のある物件は、
特定のニーズに応えることで高い評価を得ることもあります。
周辺の治安と環境
周辺の治安も、不動産の評価額に大きく影響します。
犯罪発生率が低く、安全な地域は居住者にとって安心感があり、不動産価値が高くなります。
逆に、治安が悪いとされるエリアでは、評価額が下がる傾向があります。
さらに、自然環境も評価額に影響します。
たとえば、川沿いや海近くの風光明媚なエリアは、眺望やリラックスした生活環境を求める人にとって魅力的です。
しかし、洪水や津波などの災害リスクが高い地域では、そのリスクが評価額にマイナス影響を与える場合もあります。
将来の地域開発計画
将来の地域開発計画も重要な要因です。
市区町村が進めている再開発や、新たなインフラ整備計画などがある地域では、
今後の利便性や地域の発展が期待できるため、評価額が高まります。
たとえば、新しい駅の設置や大規模なショッピングモールの建設計画があるエリアでは、
不動産価値が急激に上昇することが多いです。
一方、再開発計画がない、あるいは地域の衰退が進んでいるエリアでは、
今後の評価額の上昇は期待しにくく、投資価値が下がることがあります。
法的な規制
最後に、法的な規制です。
不動産があるエリアがどのような用途地域に指定されているかによって、
建物の高さ制限や用途制限などが課せられることがあります。
たとえば、商業地域では高層ビルの建設が許可されている一方、
住居専用地域では高さ制限があり、低層の建物しか建てられません。
また、自然保護区域や文化財保護区域などの特別な規制がある場合、
その土地の利用が制限されることがあり、評価額が低くなる可能性もあります。
不動産の評価額は、交通アクセスや周辺施設、土地や建物の状態、将来の開発計画、さらには法的規制など、
さまざまな要因によって決定されます。
これらの要因を理解し、不動産購入や売却の際には総合的に評価することが大切です。
特に、自身が重視するポイントを明確にしておくことで、より納得のいく取引ができるでしょう。
まとめ

今回は不動産評価額の意味や調べ方を中心に解説しました。
不動産評価額は、所有する土地や建物の評価額がわかる方法です。
不動産の売却や相続・贈与を受ける際は、固定資産税評価額や公示地価、基準地価など様々な指標を活用し、
不動産の価値を正確に把握してみてください。
しかし、調べた評価額は必ずしも正確な価格ではありません。
そのため、実際の評価額を調べる場合は、不動産鑑定士や不動産業者に査定してもらうことをおすすめします。
当社は50年以上不動産業を手掛けており、適正な価格を把握する不動産鑑定も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
Operating Company
- 執筆者
-
スターツコーポレートサービス株式会社 COPPO!編集部
当社の特徴-
①法人さまごとの専任体制でお客様の課題をワンストップで解決
②社宅代行約450社・約13万件、継続25年以上、寮・社宅のプロ
③80社を超えるグループ会社と国内約3000社の提携不動産会社、
海外では21カ国・30拠点以上の日経不動産会社最大級のネットワーク
法人向け不動産サービスを中心に、スターツグループのコンテンツと
独自のネットワークを最大限活用し、様々な経営課題を共に解決します
当社のサービス:社宅代行・社員寮紹介、オフィス移転、不動産売買
-
カテゴリ:
- 企業不動産戦略
-
タグ:
まずは、お気軽に今のお困りごとを
お聞かせください。
スターツコーポレートサービスでは寮・社宅に関するどんな小さなお悩みでもお受けします。
長年培った寮・社宅業務のノウハウを駆使して、法人様に合った解決方法をご提案しますので、まずはご相談ください。